左ページから抽出された内容
17総合接続図GP型1級受信機(DC24Vガス警報器電源内蔵型)ガス警報器電源の配線亘長早見表(DC24Vシステムで外部電源としてBG5203Hを使用した場合)DC24Vガス漏れ警報システムを設置する場合、ガス警報器の消費電流が大きく(DC24V、100mA)、配線抵抗による電圧降下のため、ガス警報器の最低印加電圧(DC17V)以下にならない様に設計施工する必要があります。●配線亘長とは、ガス警報器電源から最も離れたガス警報器までの 片道の距離です。●配線亘長(片道)は次の計算式で求めることもできます。102030507010020030050070010002000300012345710↑ガス警報器取付個数配線長(片道)(m)→φ0.9φ1.2φ1.6GEP警報器電源配線亘長1回路に10コまでVd 配線長(m)= ×10002×I×R×NVd:許容電圧降下(10V)I:警報器消費電流(0.1A)N:警報器接続数R:配線抵抗 0.9mm…29.2Ω/km1.2mm…15.8Ω/km1.6mm…8.92Ω/km2.0mm…5.65Ω/km注1)警報器は有電圧出力型をご使用ください。注2)警報器およびガス漏れ中継器には極性がありますのでご注意ください。注3)ガス漏れ表示灯中継器およびガス漏れ中継器で警報器を接続しない端子がある場合、結線されているわたり線は外さないでください。注4)警報器が取り外されたり警報器の電源線や信号線が断線すると、受信機の故障地区灯が点滅し、ブザーが鳴ります。注5)ガス警報器は、1系統10個までとしてください。注6)AC100V用ガス警報器を接続する場合など、受信機にDC24Vガス警報器電源を内蔵しないタイプも対応可能です。●ガス漏れ部のみ抜粋。P型1級複合受信機部は9ページをご覧ください。G+−G+−G+−G+−G+−G+G+−−G+−G+−G+−G+−G+G+−G+−G+−−G+−受信機1回線あたり1個警報器中継器中継器電源警報器中継器ガス警報器電源〔受信機に内蔵〕警報器を1回線あたり1個接続する場合警報器を1回線あたり複数個接続する場合あき回線については、結線終了後ディップスイッチを「あき」側に設定してください。終端の表示灯はΩとGlをわたり線で接続してください。1回線を表示灯により複数区画する接続方法ガス漏れ表示灯中継器は1回線あたり10個まで、受信機1台あたり30個までガス漏れ表示灯中継器1個あたりガス漏れ中継器は3個まで接続できます。AC100V専用電源より(専用ブレーカには付属のガス漏れ火災警報設備専用ラベルを貼る。)ガス警報器ガス漏れ表示灯中継器ガス漏れ中継器GL1GC1GL2GC2GS+GL3GC3GSG+1G−1G+2G−2G+3G−3G+1G−1G+2G−2G+3G−3G+1G−1G+2G−2G+3G−3ΩGIGOGCGCガス漏れ表示灯中継器GSΩGIGOGCGCGL4GLnBP1BP2BG1+BG1−BG2+BG2−G+5G−5G+4G−4GLGCガス漏れ中継器G+5G−5G+4G−4GLGCG+1G−1G+2G−2G+3G−3●内蔵ガス警報器用電源の警報器配線長について (BGJ37□□3H・BGJ38□□3H・GP型受信機で共通) ガス警報器の接続数と配線亘長(片道)は次の式で求めることができます。26500配線長(m)=R×NR:配線抵抗0.9mm…29.2Ω/km1.2mm…15.8Ω/kmN:ガス警報器接続数
右ページから抽出された内容
18自動火災報知設備にも寿命があります。受信機の場合、交換の目安は15∼20年です。蓄積型非蓄積型BVJ33□□、BVJ34□□BVF35□□HK、BVF37□□H、BVF36□□FK、BVF38□□F受第10∼28号2000年BVJ17□□、BVJ18□□BVF11□□HK、BVF13□□H、BVF12□□FK、BVF14□□F受第10∼28号2000年BZJ1、BZJ9受第10∼38号1999年BZJ1、BZJ9BVE13□□H、BVE16□□H、BVE33□□H、BVE36□□H等仕様内容による受第6∼10∼1号1999年BVJ31□□、BVJ32□□BVF35□□HK、BVF37□□H、BVF36□□FK、BVF38□□F受第6∼10号1999年BZJ1、BZJ9受第10∼37号、受第10∼39号全部品1999年BZJ1、BZJ9受第6∼18∼1号全部品1998年BZ1、BZ9BZE11、BZE12、BZE91、BZE92等仕様内容による受第61∼37号全部品1990年BZ1、BZ9受第61∼28∼1号全部品1995年BZ1、BZ9受信機15年(※20年)※電子機器部品を多用していない機器。地区音響装置20年発信機20年熱式感知器15年熱式感知器(半導体式)10年煙式感知器10年BZF14、BZF15、BZF94、BZF95等仕様内容による受第61∼28号全部品1995年BVJ15□□、BVJ16□□BVF11□□HK、BVF13□□H、BVF12□□FK、BVF14□□F受第6∼10号1999年BVJ12□□受第5∼3号1999年BVJ11□□BVJ101□□HKBVJ101□□1K受第5∼3号1994年BZ1、BZ9仕様内容による受第60∼40∼3号1993年BZ1、BZ9受第60∼40∼2号1993年BV26□□□□BVF35□□HK、BVF37□□H受第60∼40∼2号1988年BZ1、BZ9仕様内容による受第60∼40∼3号1993年BV19□□BVF12□□FK、BVF14□□F受第60∼40∼2号1988年BV18□□KC受第60∼40∼2号1993年BV18□□K受第60∼40∼2号1988年BV18□□BVJ101□□HKBVJ101□□1KBVF11□□HK、BVF13□□H受第60∼40∼1号1986年BZ1、BZ9受第54∼28∼3号1985年BZ1、BZ9受第54∼28∼2号1985年BZ1、BZ9仕様内容による受第54∼28号1985年BV23□□□□J受第54∼28号1986年BV23□□□□BVF35□□HK、BVF37□□HBVF36□□FK、BVF38□□F等受第54∼28号1985年BZ31□□□□受第54∼28号1985年BV17□□受第54∼28号1987年BV16□□、BV17□□BVJ101□□HKBVJ101□□1K等受第54∼28号1987年BV21□□□□K受第51∼6号1982年BV21□□□□BVF35□□HK、BVF37□□HBVF36□□FK、BVF38□□F等受第51∼6号1979年BV15□□受第51∼6号1982年BV14□□受第47∼10∼3号全部品1976年BV11□□商品品番国家検定番号供給が困難代替品生産終了BVJ101□□HKBVJ101□□1K等受第47∼10号全部品全部品全部品全部品全部品全部品全部品全部品全部品全部品全部品全部品全部品全部品全部品全部品全部品全部品全部品全部品全部品全部品全部品全部品全部品全部品全部品全部品BVF16□□BVF13□□H受第12∼1号2004年BVJ13□□BVJ101□□HK、BVJ101□□1K受第10∼27号2004年全部品全部品BVF31□□、BVF32□□BVF35□□HK、BVF37□□H、BVF36□□FK、BVF38□□F受第12∼1号2002年全部品BVF32□□KBVF37□□H受第12∼1号2004年全部品1975年P型1級受信機・P型1級複合受信機商品品番国家検定番号供給が困難代替品生産終了GP型1級受信機部品供給困難品一覧(P型1級受信機・P型1級複合受信機・GP型1級受信機)既設の自動火災報知設備機器の更新について更新の目安は10年∼20年です。自動火災報知設備の一部は法改正、型式失効制度、定期点検などによって設備の更新が行われていますが、その機能と性能の信頼性を維持するには経時的な限界があり、設置から一定期間を経過した設備は更新する必要があります。一般社団法人日本火災報知機工業会では、約4000件の点検物件から不具合などで交換された機器の調査データに基づき、自動火災報知設備の主要機器の更新期間を右記のように設定しています。15年以上ご使用いただいている受信機は、経年劣化などにより故障が発生する可能性が高くなっています。また、補修部品の供給も次第に困難になってきています。以下の受信機はすでに生産終了後20年を経過しておりますので、設備更新を推奨します。注1)2020年10月現在の内容です。今後、供給困難となる補修部品が出てくる場合がございますので、あらかじめご了承ください。注2)代替品は同等の基本性能を有する品番を掲載しておりますが、形状・寸法・その他仕様は異なる場合があります。また、交換時は接続されている関連機器も合わせて交換が必要になる場合がありますので、ご注意ください。注)上記の参考年数は、適切に定期点検が実施され、機器の設置環境に支障がない場合です。(設置場所の設置環境によっては、状況により短くなる場合があります。)ガス警報器5年一般社団法人日本火災報知機工業会既設の自動火災報知設備機器の更新についてフレキシブルP-1シリーズが該当リニューアルのご案内

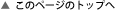


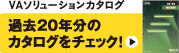


お探しのページは「カタログビュー」でごらんいただけます。カタログビューではweb上でパラパラめくりながらカタログをごらんになれます。