左ページから抽出された内容
感震ブレーカー ご採用・納入事例住宅販売会社様南海トラフ震災の懸念に必要性を確信リスク対策とコストのバランスが採用の決め手■ご採用の背景丸良木材産業株式会社様可能な対策に真に取り組み日々の暮らしにお客様へ安心を提供。「これは弊社に必要だ」と確信、感震ブレーカーを標準採用「私が感震ブレーカーを知ったのは2015年です。当時、阪神・淡路大震災の際には通電火災が多かったことも聞いていました」と髙森様。「弊社の商圏は南海トラフ地震が懸念される和歌山県です。感震ブレーカーを知った瞬間、『これは弊社の家に必要なものだ』と確信しました」その思いは、採用について検討する必要性さえ感じなかったほどだそうです。「ちょうど通電火災の対策に困っていたところでしたが、感震ブレーカーは2006年の発売だとか。勉強不足でしたね」「以来、弊社では感震ブレーカーを標準仕様にしています。もちろん、標準採用だからといってお客様に褒めていただくことはなく、他社と差別化できるわけではないかも知れません。ですが、むしろ私たちにとって感震ブレーカーがついていること自体が、電気ストーブに安全装置があるのと同じくらい、当たり前だと思っています」予測ができないからこそ、可能な対策には真に取り組む「阪神・淡路大震災のあと『次は南海トラフ地震だ』と言われていましたが、その後は日本各地が災害クラスの地震に見舞われました。大きな地震は起きないと言われ、他の地域よりも耐震性の低い建築が許容されていた九州にさえ地震が起きました。専門家でも地震の時期や場所、大きさなどは予知できないこと、日本全国どこでも大地震が起きうることが明らかになったのだと思います」と髙森様。「和歌山の場合も、専門家の意見だけに頼れなくなったことと、いつ起きても不思議ではないという不安が一層強まったように思います」と、備えについての重要さを強調されています。「残念ながら、すべての災害に対して、住む人の命を守り、またその後の不安も持たせない家というのは、現時点ではまだ難しいかも知れません。だからこそ対策が可能な災害に対しては、できる限り真に取り組み、日々進化していきたいと考えています」耐震ブレーカーは、リスクとコストのバランスが取れた備え「地震に対する意識は以前から高く、地震に強いテクノストラクチャー工法は弊社の主力です。感震ブレーカーの他にも、耐震ダンパーも標準仕様に加えています」と髙森様。「1棟ごとに地震時の耐久力の計算(構造計算)を行うテクノストラクチャー工法を採用する弊社のコンセプトは、『日々の暮らしの中で、お客様に安心を感じていただける家を提供する』ことです」「お客様が感じられる不安にはさまざまなものがありますが、少なくとも、大きな災害が起きたらどうしようという不安は消して差し上げたい。家族のけがに対する不安だけでなく、その後の生活に対する不安も消して差し上げられるような、そんな家づくりを考えています。地震への備えの他にも、瓦を『台風でも飛びにくい瓦』から『台風でも飛びにくく、かつ割れにくい瓦』に変更しました。最近の瓦は高い耐風強度が出るように設計されていますが、よそからの飛来物などで割れてしまうと設計通りの耐風強度が出ず、周囲に飛散することがあるためです」「災害に対しては、個々人が危機意識をもって備えるのが理想ですが、将来起きるかもしれない災害への備えよりも、目の前のことにお金を使いたくなるのも人情でしょう。逆に防災に意識が向きすぎても、災害に対する完璧な備えといったものがない以上、考えるほど不安ばかりが増えて行くことにもなりかねません。備えで一番大事なことは、リスクとコストの適切なバランスを見つけ、実行することだと思います。私たちが専門家としてこのバランスを考え、必要な備えを標準仕様としてご提案するのも一つのやり方です。その観点で見たとき、感震ブレーカーは大変コストパフォーマンスに優れた、標準仕様への採用が容易な商品だと思います」丸良木材産業株式会社 社長髙森様
右ページから抽出された内容
熊本地震の経験、南海トラフの懸念安全・安心のための基本設備として全棟に標準採用■ご採用の背景株式会社建築工房小越様施主様の家の主治医として安心して住んでいただける家を提供する。災害の状況を知り、地震に強い家の重要さを痛感「私はパナソニックが主催する『くらし体感スクエア』で感震ブレーカーを知りました」と小越社長。「通電火災についてはそれまでも聞いたことはありましたが、『くらし体感スクエア』では、その割合などがはっきりとデータを示されていて、対策の必要性を強く感じました。正直、この価格で通電火災への備えができるのであれば、感震ブレーカーを採用するべきだと思います」現在は同社で工務を担当されている小越社長のご子息が、大学の地震研究室に在籍していたときに熊本地震が起きました。小越社長はご子息の活動を通して地震直後の状況を目の当たりにされ、いかに地震に強い家が重要であるかを痛感されたそうです。建築工房小越様では、揺れに強い耐震等級3に加え、揺れを軽減させるための制振装置が標準仕様になっています。熊本地震の2度に渡る震度7を経ても倒壊しなかったのが耐震等級3の住宅です。家づくりのプロとして、安全を提供できない住宅は売れない「今後30年以内に南海トラフで地震が発生する確率が70∼80%あると言われています。地震は起きるかも知れないではなく、必ず起きると考えて備えをしておかなければいけません。弊社では『予算の都合で耐震等級を下げたい』という要望は、申し訳ありませんがお断りしています。家づくりのプロとして、お客様へ安全性を提供できない住宅を売ることはできません。また、耐震性を高めた家でも、家は倒れなかったが通電火災で火事が発生した、ということになってはいけない。まず地震が起こっても倒れないこと、そのうえで感震ブレーカーが通電火災を防ぐことにより、災害後スムーズにご自宅での生活を始められる住宅を提供したいと考えています」感震ブレーカーはオプションではなく、安心の提供に必須のもの「感震ブレーカーが本当に評価されるとすれば、実際に震度5強以上の地震が発生したときかも知れません」残念ながら通電火災を意識しているお客様はまだ少なく、小越社長はそうしたことも説明したうえで安心して住んでいただける家を提供したいと考えておられます。「耐震等級3や制振装置、それにこの感震ブレーカーは、単なるオプションではなく、お客様に安心・安全を提供するために必須のものです。私たちは、これらを住宅の基本的な設備として全棟に標準採用すべきだと考えています」「住宅の一次取得層は年齢も比較的若く、やはりデザインと価格のバランスに優先順位が高くなりがちです。それでも、50年、60年暮らしていく中でのトータルのランニングコストについて説明すれば、半数以上の方は考えが変わります。初期コストが多少上がっても長持ちする家であることや、消費電力の見える化などで、ランニングコストの観点からエネルギーマネジメントの重要性も理解されるようになる。安心・安全に長持ちする家に住み続けていただくためにも、弊社は『施主様の家の主治医』であるべきだと思っています」株式会社建築工房小越社長小越様

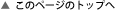


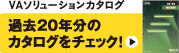


お探しのページは「カタログビュー」でごらんいただけます。カタログビューではweb上でパラパラめくりながらカタログをごらんになれます。