左ページから抽出された内容
納入事例 糸魚川市駅北大火復興まちづくり「糸魚川らしいまちなみ」「防災を意識した基盤づくり」を検証。VRを活用した対話で被災住民の想い、意見、アイデアを反映。地域再生プロジェクト古くは宿場町として栄え、民地を活用した雪よけの屋根「雁木」に街道のまちの風情が漂う歴史的なまちなみの糸魚川市。平成28年12月22日(木)糸魚川市駅北エリアで大規模火災が発生。30時間後に鎮火したが全焼120棟を含む147棟の家屋が被害を受け、日本全国に大きく報道された。平成29年度から5年の期間を「復興計画期」「復興整備期」「復興展開期」に分け復興まちづくりが計画され、「災害に強いまち」「にぎわいのあるまち」「すみ続けられるまち」の3つの方針のもと、復興まちづくりに対する考え方を共有しながら、被災住民、事業者、市民の意見を取り入れたまちづくりを推進するにあたって、VRが大いに活用された。また本件は国の社会資本整備総合交付金による補助対象事業とすることで、VRシステムの導入経費負担の軽減が図られた。大火前のまちなみのVRイメージ復興まちづくり計画全体のVRイメージ実際に再建された糸魚川のまちなみ写真(2019年時点) 大火後のまちなみのVRイメージどこの街でも起こり得る身近な災害からの復興計画を被災住民、事業者、市民と一体となって推進。「雁木」のある糸魚川らしいまちなみ再建のVRイメージ
右ページから抽出された内容
被災者関係者説明会や、10世帯程度を一つのグループに分けたブロック別意見交換会にて、市職員がVRデータを実際に動かしながら、説明・意見交換に活用されている。初期のVRイメージ整備後の実際の写真住民の意見を反映したVRイメージ復興計画の推進にあたって、市と被災住民との間の意見交換・事業調整にVRを効果的に活用。ブロック別意見交換会でのVR活用の様子 被災者関係者説明会の資料に活用住民の意見が反映された小路・市民広場糸魚川市産業部復興推進課渡辺茂様丁寧な推進が求められる復興計画VRが被災住民のまちづくりへの主体的な参加を促す従来では考えられなかった柔軟な対応が可能に復興の現状とこれから災害からの復興計画の推進にあたっては、家屋だけでなく心にも傷を負われた被災住民の方に対して、きめ細やかな対応が必要でした。被災地を街区のまとまりごとに分割し、市の復興事業に関する意見交換会を実施。災害に強く、糸魚川らしいまちなみを活かしたまちづくりを、視覚的にわかりやすく説明するためにVRを活用しました。被災された方にとっては、自宅の再建と市の復興事業が同時に進められるわけです。先の火災では、家屋の密集とオープンスペースの少なさが延焼の一因でもあったため、公園や広場などの整備を市で計画。そうした公共空間と家屋との間に、高さ1.8mほどの板塀の設置を検討し、VRでご確認いただきました。すると「日差しが入らなくなるので高さを抑えてほしい」「防犯上の死角になるので塀はいらない」「冬は雪を捨てるので完全に足元まで覆わないでほしい」といった、生活目線からの声が寄せられ、計画に反映していきました。今までだと平面図や立面図しか説明する手段がなく、それも市の建造物しか表現ができない。それだと一般の方にはイメージがしづらく、なかなかご理解いただけませんでした。VRなら、市が計画する公共空間と個人の家屋との関係性まで忠実に表現でき、市の事業と個人再建の擦り合わせが円滑に進みました。一方で、イメージが明確に伝わる分、実際の整備後の仕上がりと差異が生まれないよう、色合いや位置関係の微調整を繰り返し行いました。対外的な説明用途以外にも、VRはそうした内部検討のための調整に役立ちました。加えてVRにはJPG画像の切り出し機能があるので、被災者説明会や市議会で使用する資料づくりの効率が格段に上がりました。住環境の整備は落ち着きましたし、今は伝統的な雁木の再生や無電柱化の工事が進んでいます。これで復興まちづくりのハード面の事業は一区切りとなります。VRはその過程で、仮想の都市基盤をデータベース化することに貢献してくれました。将来的にはVRをさらに活用して、新しいまちづくりのシミュレーションや、江戸∼明治時代の雁木造りのまちなみを再現した教育ツールとしても使えるかもしれませんね。

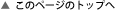


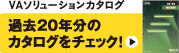


お探しのページは「カタログビュー」でごらんいただけます。カタログビューではweb上でパラパラめくりながらカタログをごらんになれます。